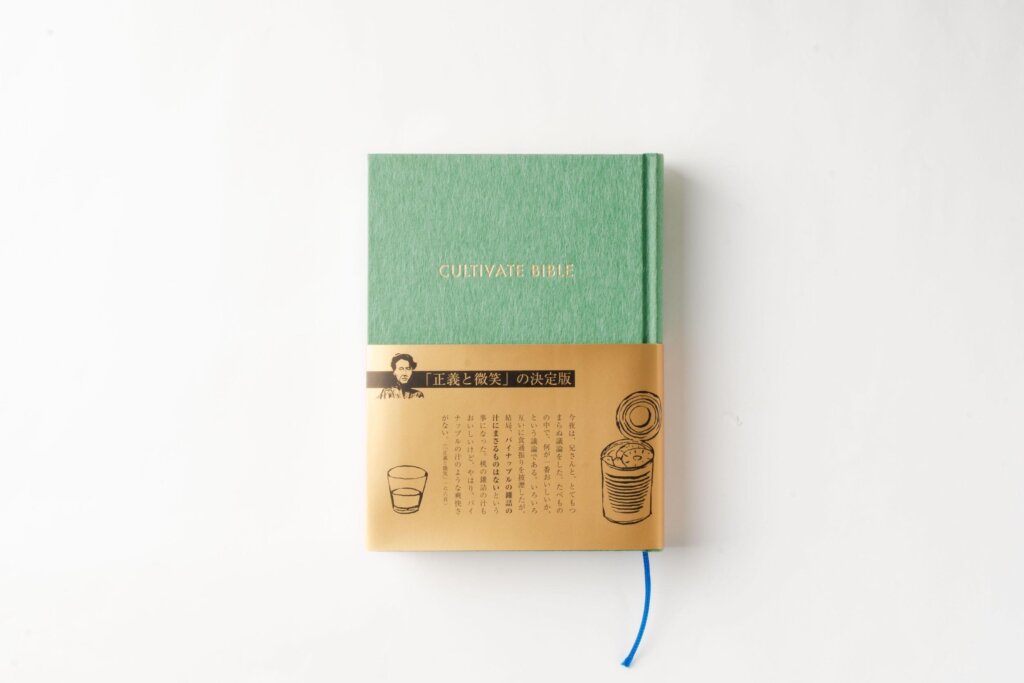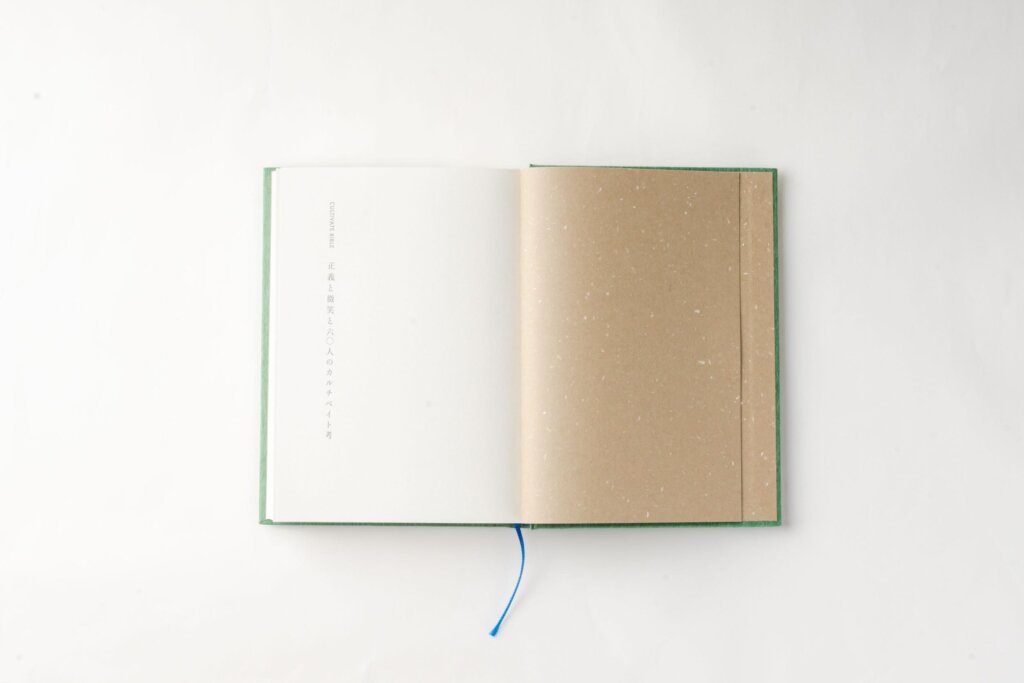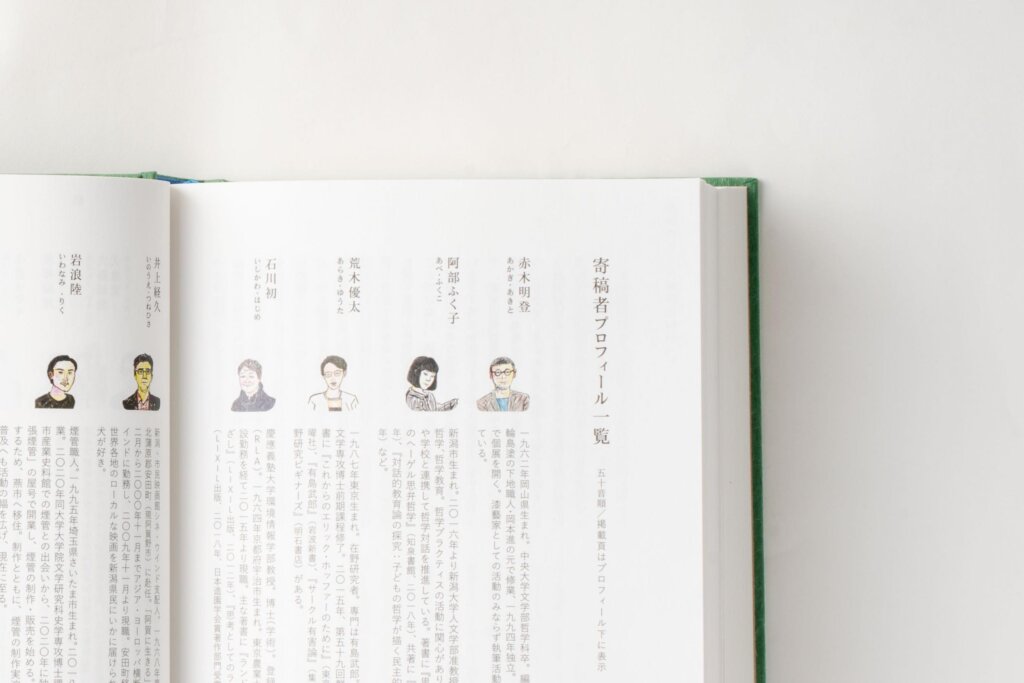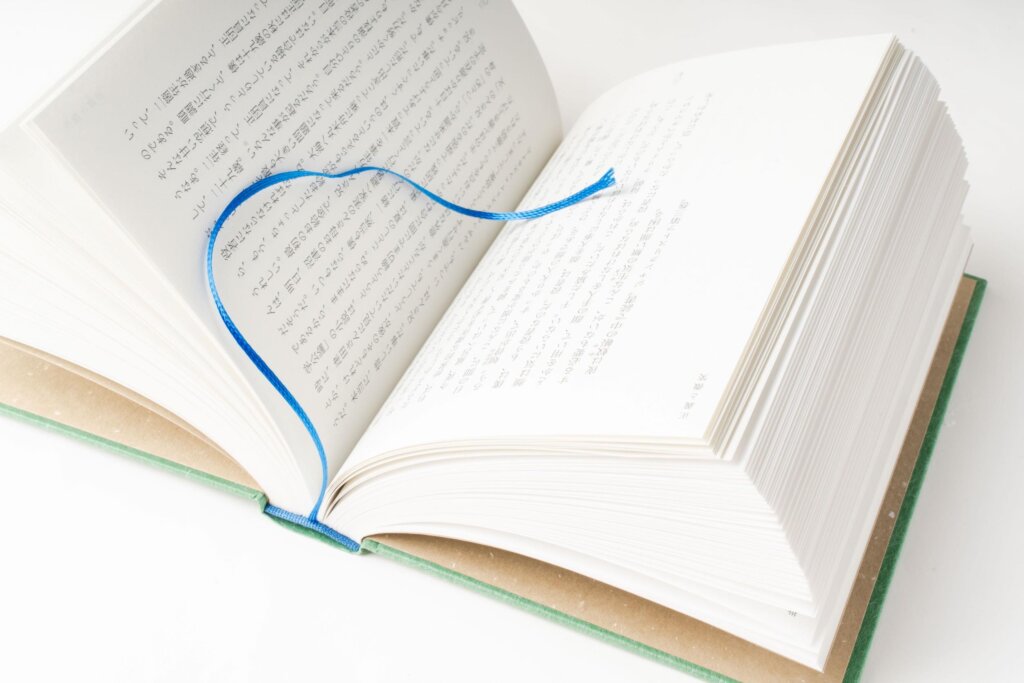銅鍋づくり体験の折に、「もっとこんな銅器をつくってみたい!」とゆうお声をいただき。何かできることはないか?とずっと考えておりましたが、一昨年に取得した石瀬の家を活用することで、そこに道場を構えることができるのではないかと考え、仲間と共にこの場をつくりあげ、この度、鎚起銅器を開設することができました。
この度、2月の末に、2泊3日で滋賀県より3名の方々に参加いただきました。

鎚起銅器は、一枚から叩き起こし器をつくる技術。ご参加の皆さんにも1枚の銅板から始めていただきます。
銅は、叩くと硬くなり、火にかけると柔らかくなる。その性質を利用。銅板を柔らかくすることを「焼き鈍し」と言います。
鉄などは、熱間加工と言い、熱して赤くしながら叩くイメージがあるかと思います。銅の場合は、焼き鈍しした後に水の中に入れて様しても柔らかいままなので、手に持っての加工ができ、加工性が高いと言われています。

先ずは、木台で立ち上げ切っ掛けを作り、その後鉄の棒の上で、金鎚で叩く。銅鍋づくり体験では、この木台と木槌だけで形をつくっていますが、道場では焼き鈍しの設備があるために、金鎚を使うことができます。
焼き鈍しをしては金鎚で叩く、ひたすらそれを繰り返して器を立ち上げてゆきます。
今回は、ミルクパンとちろりの製作。事前のmailのやり取りで図案をいただき、その図案をもとに私が寸法を計算し、板を切り出します。鎚起銅器では、背の高くなるほど手間のかかる作業。そして、材料の寸法も大きくなります。
地味な作業ではありますが、ひたすらに繰り返す中で、徐々に変化してゆく銅器を叩く時間は、目の前のことに集中し無心になる時間でもあるようです。
1日目は、終了。

2日目をひたすらに叩く。

ミルクパンの皆さんは、下部分の丸みを出すために、内側から木槌で叩きフォルムを見ながら形をつくってゆきます。
そして、口の寸法が図案の大きさになるまで、また只管に金鎚で叩く。
ある程度の形が見えながら、二日目終了。
みなさん1日、頑張ってくれました。

さて、最終日。
大まかな形が完成したら、最後は木槌で整え、綺麗な金鎚で叩き、製作過程でできた鎚目を整えてゆきます。これを「均し」作業と言います。均しというだけに、製作途中で差が出た銅の肉厚を叩いて均一にしてゆく作業です。

その後、口をつけたり。取っ手をつけたら、形は完成。
最後の仕上げに入ります。

銅は、磨けば新品の10円玉のようにピカピカになります。その分、指紋がつきやすくなります。鎚起銅器では、仕上げをすることで、何十年分かの経年変化を器全体にさせることで、安定した状態にします。
先ずは、綺麗に磨き、硫化カリュウムにつけ込み、黒くします。

その黒くしたものを残して、そのままで仕上げを終えることもできますし、磨き落として、緑青硫酸銅で煮込むことで、茶色に仕上げることもできます。

こちらは、緑青硫酸銅での煮込み作業。

お好きな色。と言われても最初の作業だとどんな風に変化してゆくのかわからないと思いますが、自然色として使っていくうちに変化してゆくもの。しかし、ピカピカな銅器よりも、このような仕上げをした銅器の方が色の成長がよいようです。
こちら、みなさんの作品。
銅鍋づくり体験西日本ツアーで主催をしてくださり、何度も経験してくださっている中で、今回も諦めずに一生懸命叩いてくださった想いが、この形になっています。
それぞれの表情があり、慈しみを感じます。私は慣れてしまい、このような表情を出すことはもうできなくなっただけに、みなさんの作品を見せてもらうことで、初心を思い出させてくれます。
私の経験をお伝えしながら、初心を思い出させ出させてくれる鎚起銅器道場。これから、どんな風に成長してゆくのか、みなさんも一緒に育てていってくだされば幸いです。
昨年より、始まりまったこの鎚起銅器道場開設に向けての準備。新潟市北区の建築士 アトリエnicoの羽ヶ崎章さん、出雲崎の木工作家 Ojn Handmade Hut ワダヨシヒトさん、長岡の鍛造所 渡辺さん、大工のマーシーさんにご協力いただき、また、新潟県のチャレンジ補助金(申請中)を活用させていただくことで、このような形にすることができました。
昨年の夏には、三和土や漆喰塗り、レンガ張りも多くの方にご協力いただき、ありがとうございました。
ご協力いただいた皆様にも、また、成長した道場の姿をご覧いただけたら幸いです。
こちらは、参加者さんから送っていただいた画像。
焼き鈍しと叩きを何度も繰り返し、形になってゆく様がわかりやすいものをいただきました。
またのお越しを、心よりお待ちしております。