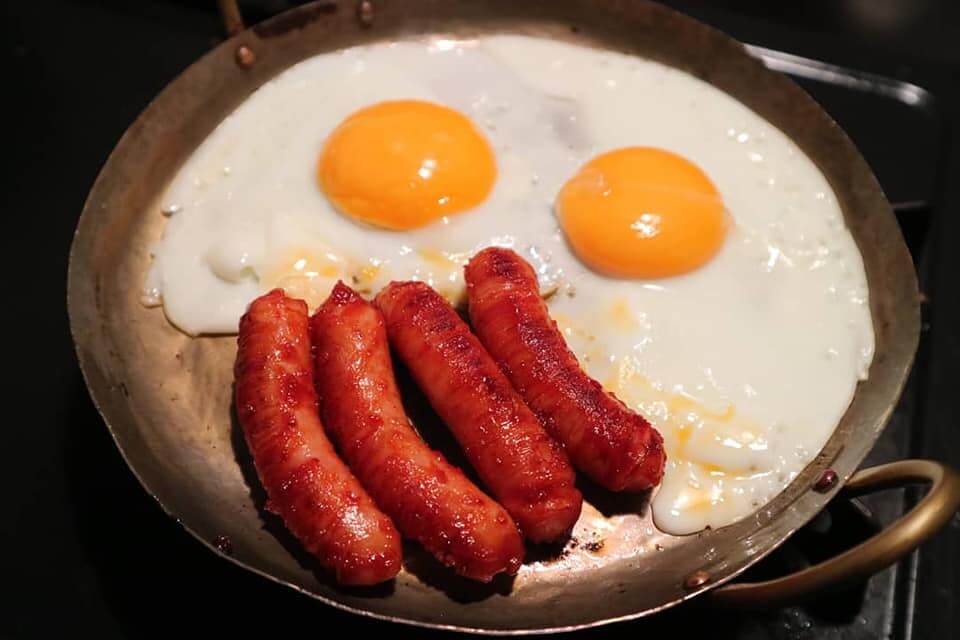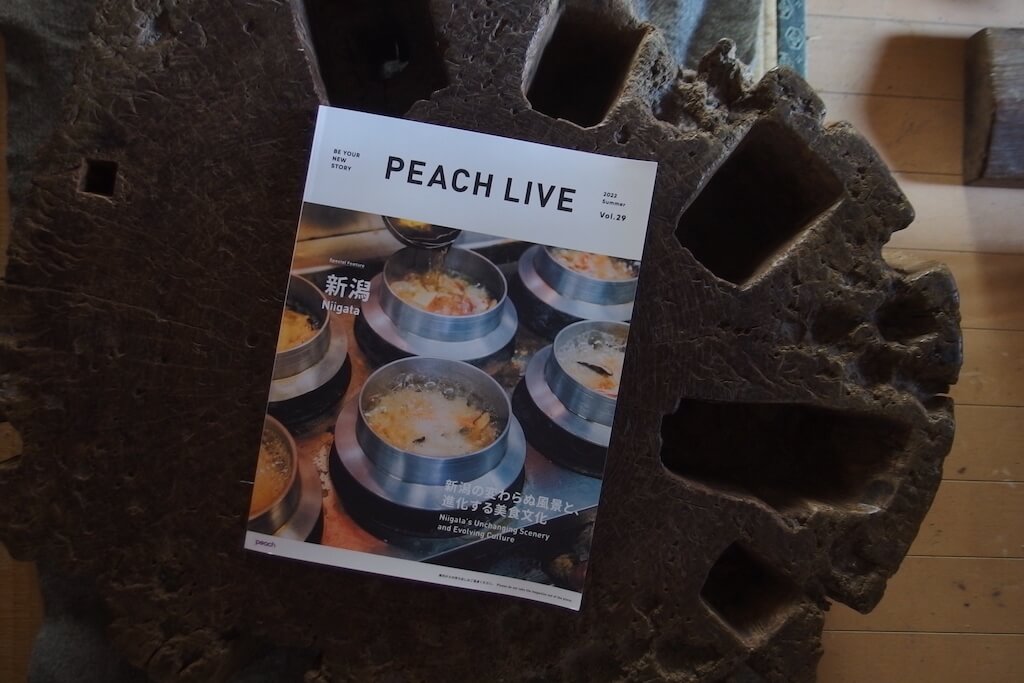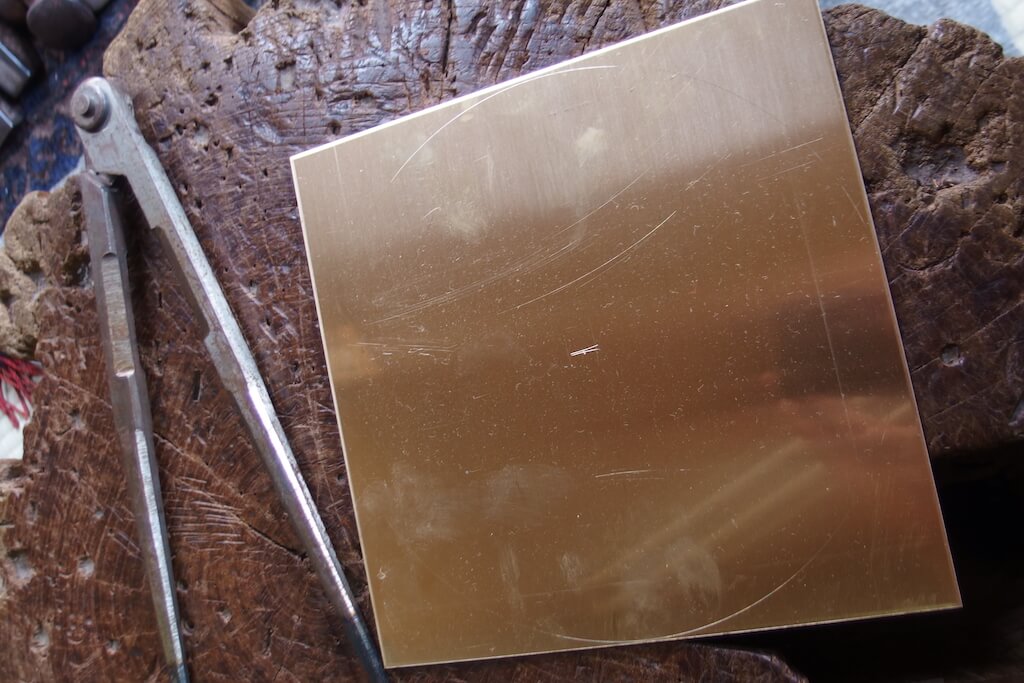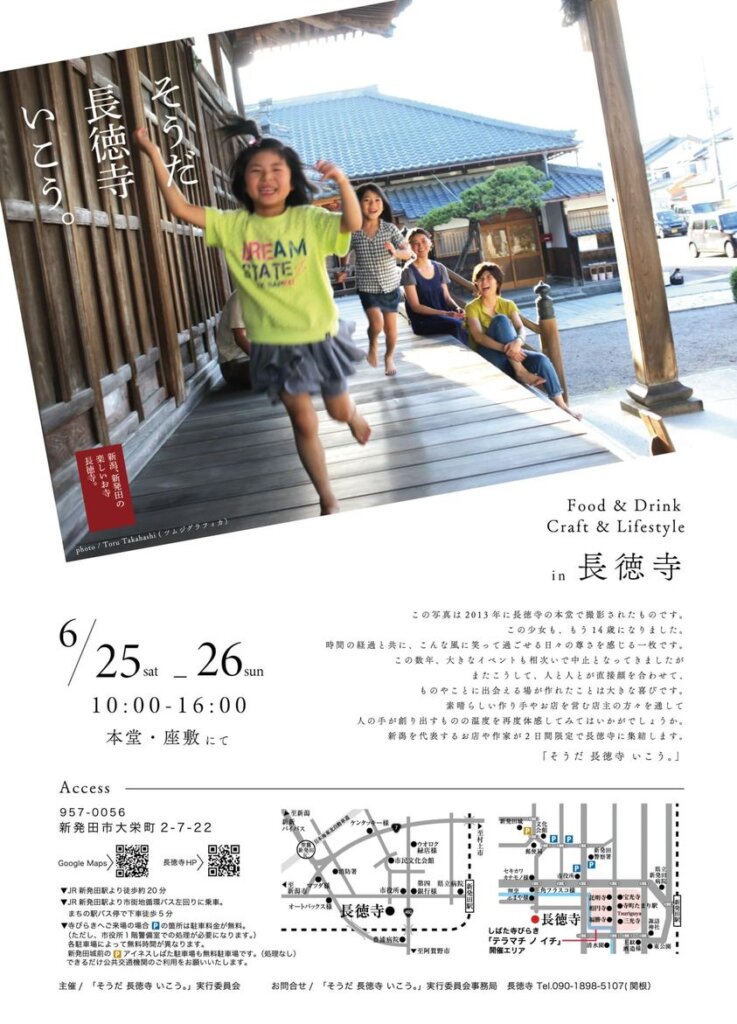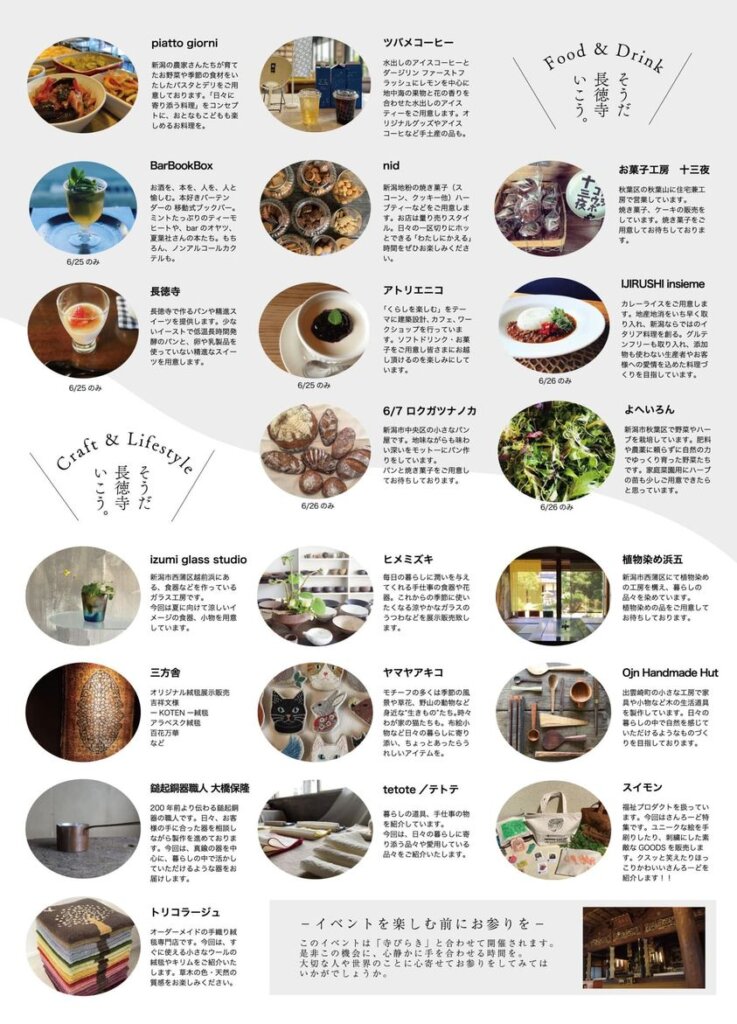2022年秋 西日本ツアーの日程

この秋も、滋賀から鹿児島へと銅鍋づくり体験を西日本各地で開催していただくことになりました。
お陰様でこのツアーも福岡に伺い始めてから5年となりました。
今回は、25周年とゆうことで、いつもより多めに巡らせていただきます。
各地での詳細は、FBイベントページでご確認ください。
また、参加者さんがご自身でつくりだした銅鍋でお料理をされているFBグループ 鎚起銅器てづくり銅鍋愛好会もあります。みなさんの楽しんでくださっている模様がとても嬉しいページです。「どんな銅鍋をつくりたいのか?」参考にしていただけたら幸いです。
9月
7日水曜 滋賀 https://www.facebook.com/sachihiraki715
8日木曜
9日金曜
10日土曜 名古屋 https://www.facebook.com/events/1516596255437474/
11日日曜
12日月曜
13日火曜 移動
14日水曜 移動
15日木曜 福岡 https://www.facebook.com/events/828840861436483
16日金曜 福岡 https://www.facebook.com/events/828840861436483
17日土曜 福岡 https://www.facebook.com/events/828840861436483
18日日曜 移動
19日月曜 熊本 https://www.facebook.com/events/828840861436483
20日火曜 熊本 https://www.facebook.com/events/828840861436483
21日水曜 移動
22日木曜 移動
23日金祝 霧島 満席
24日土曜 霧島 満席
25日日曜 岡山 https://www.facebook.com/events/408396534513050
26日月曜 移動
27日火曜 今治 https://www.facebook.com/events/5777881545607888
28日水曜 大阪 https://www.facebook.com/events/603559017875429
29日木曜
30日金曜
10月
1日土曜
2日日曜 堺 https://www.facebook.com/events/758578332035751
3日月曜
4日火曜
5日水曜 滋賀 https://www.facebook.com/events/s/398248529087102/
また日程の空きの日もありますので、ご自身の地元で主催をしてくださる方が居られましたら、お気軽にご連絡ください。
詳細は、以下より。
銅鍋づくり体験の模様https://tsuiki-oohashi.com/2019/07/11/3122/
銅鍋づくり体験についてhttps://tsuiki-oohashi.com/2019/01/13/2361/
皆様のご参加を心よりお待ちしております。